
「今の就活、本当にこのままでいいのかな」
「内定をもらっても、やっぱり他の道も気になる」
そんなモヤモヤを抱えながら、就活と並行して転職活動を検討する学生も少なくありません。
しかし、活動の軸が曖昧なまま進めてしまうと、どちらも中途半端になってしまう不安がありますよね。
この記事では、キャリエモンQ&Aに寄せられたリアルな悩みをもとに、就活と転職活動をうまく両立させるための考え方や、書類・面接対策のポイントを具体的に解説します。
納得できる結果にたどり着けるよう、あなたの迷いを一緒に整理していきましょう。
就活と転職活動を両立するために、活動の軸を明確にする
就活と転職活動を両立させるには、まず「自分は何を軸に働きたいのか」を明確にすることが大切です。
「やりたいことが定まらず、なんとなくエントリーを続けてしまっている…」という人も多いのではないでしょうか。
そんなときは、過去に夢中になれたことや、やりがいを感じた経験を振り返ることがヒントになります。
自分にとって「譲れない思い」や「迷いの正体」を言語化することで、キャリアの方向性が少しずつ見えてきます。
この記事では、後悔のない選択をするために、軸を整理する具体的なポイントを紹介します。
1.転職活動の軸を整理する
転職活動を始めると、気になる企業を探したり、条件を比べたりと、どうしても希望がブレてしまいます。
まず向き合いたいのは「自分は何に夢中になれたのか」「どんな価値観を大切にして働きたいのか」というキャリアの軸です。
ここでは、キャリエモンQ&Aの相談をもとに、軸を見つけるヒントを整理していきます。
【相談内容】
現在、教育魅力化コーディネーターという職で仕事をしています。
地域社会と高校を繋ぐ役割ということで働いていますが、実際あまり仕事がなく成長も実感できないため転職を検討しています。
最終的には、学校教育と社会をつなぐ役回りを果たしたいと考えていますが、そのためにどのような職種を経験すれば良いかわかりません。
求人票を見ていると、法人営業もいいな、Webマーケットもいいなとなってしまっていて、軸が定められていない状況です。お客様のニーズを把握し、それを解決する仕事がいいのかな、と思っています。
それか、教育の世界でこのままキャリアを積んでいくのかも考えています。 転職の軸を定めるには何をしたら良いのでしょうか。
転職の軸に悩む相談に対しては、2つのアプローチで考えることができます。
今までの経験を“動詞”で洗い出す
- 苦なく夢中で取り組める領域を特定する
- 自身の強い思いは何がそうさせるのかを抽象化していく
- そのうえで方向性を見出す
自分の迷いから方向性を見出す
- 自身の中にある迷いを文字に書き起こす
- その内容を分析する
- 結果として方向性が見えてくる
どちらの視点も、自分らしい選択を見つけるうえで役立つヒントです。
ひとつずつ見つめ直せば、あなたにとって「しっくりくる選択肢」が、きっと見えてくるはずです。
「自分の軸が分からない」と感じたときの考え方については、以下のQ&Aで具体的にアドバイスしています。
参考にしてみてください。
2.段階的なキャリアプランを描く
「やりたいこと」や「実現したい目標」は見えているものの、そこに至る経験の積み方に迷う人も少なくありません。
今回キャリエモンQ&Aに寄せられた相談も、まさにそうした悩みを抱えたケースです。
【相談内容】
私のキャリア最終目標
世界中の都市だけでなく、地方の個人商店にまで貴社の商品を広めたい
<質問>
最終目標は決まっているのですが、この目標に向けてどのようにキャリアを描けばいいかを教えていただきたいです。現在は国内営業→海外営業を考えており、国内営業の経験から得られる市場のニーズや売り場づくりを海外営業に活かしたいと考えています。
また、考えとしてまとまっていないことは、マーケティングや広報にも興味があり、私の最終目標を達成するためには、新しい商品の企画に携わり、現地の嗜好に合わせたお菓子を発売することや広報の活動も不可欠だと考えています。
しかしこれをどこに落とし込めば良いのか悩んでいるため、アドバイスを頂きたいです。よろしくお願いいたします。
最終目標を掲げ、その実現に向けたキャリアの描き方や、マーケティング・広報への興味をどのように伝えたら良いか悩んでいると分かります。
このケースでは、面接などで以下の内容を伝えることを意識しましょう。
- あくまで「営業職として結果を出すことが1番」
- 自分自身のスキルを向上させて、志望企業にプラスになるようにしたい
- 上記2点をふまえ、営業職で身につくスキルとマーケティング・広報職との関連性
- 自身・企業の成長をどちらも叶えるために、その一歩先を見据えて働きたい
まずは、目指す目標に向けて、今できることからひとつずつ丁寧に積み上げていく姿勢が、企業にも伝わるキャリアビジョンにつながっていくでしょう。
将来やりたいことが明確になっているのであれば、すぐに全てを叶えられなくても、段階的に近づいていけます。
以下のQ&Aでは、面接でのキャリアパスについて具体的にアドバイスされています。
自分のキャリアプランをどう整理し、どんな順序で伝えていけばいいのか迷ったときは、ぜひ参考にしてみてください。
就活と転職活動を両立させるための志望動機と転職理由の伝え方を整える
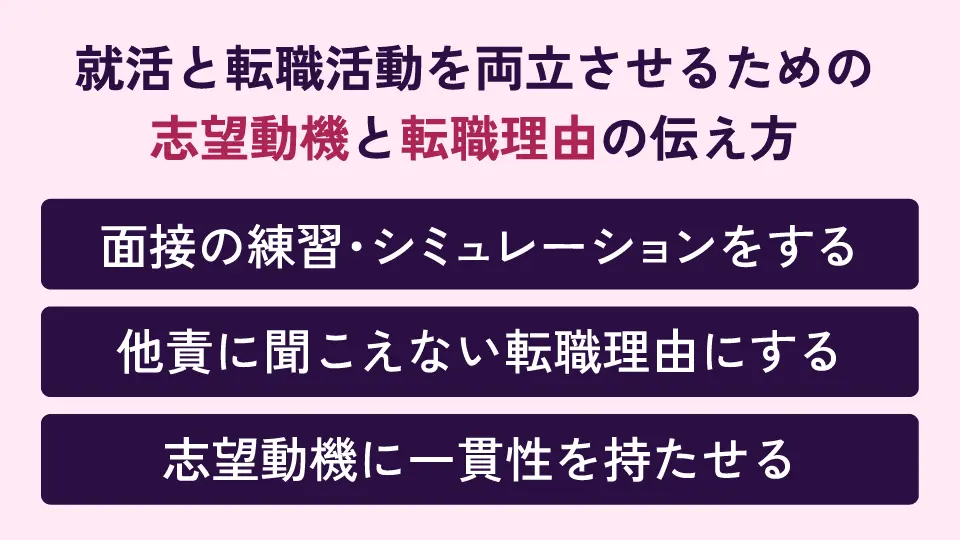
就活と転職活動を並行して進める中で、多くの人が悩むのが「どう伝えるか」の部分です。
面接やエントリーシートで、自分の想いや背景を正しく、かつ前向きに伝えられるかどうかは、選考の印象を大きく左右します。
特に、転職理由や志望動機については「ネガティブに捉えられないか」「一貫性が伝わるか」など、不安を抱きやすいものです。
そこで、キャリエモンQ&Aに寄せられた実際の相談をもとに、次の3つの視点から「伝え方」を整理していきます。
- 面接でうまく話せるようにするための練習・シミュレーション
- ネガティブに聞こえないように工夫された転職理由の伝え方
- 転職と就活の間に一貫性のある志望動機を持たせる方法
面接の練習・シミュレーションをする
面接で「準備していたはずの内容がうまく話せなかった」という悩みは少なくありません。
キャリエモンQ&Aには想定回答をまとめて臨んだものの、本番では別のことを話してしまい、うまく伝えられなかったという相談が寄せられていました。
【相談内容】
先日,とある企業のインターン面接を受けましたが,全体的に言葉がまとまらず面接官とのコミュニケーションがうまくできていないように感じました.
面接自体には念入りに準備をしており,想定の回答集もまとめた状態で挑んでいました.
ただ,実際に質問が飛んでくると,本来回答すべき内容(準備した内容)とは別のことを言ってしまうことが多かったです.
1人で発言する練習などをしてはいますが,他に効果的な練習方法や考え方があれば教えていただきたいです.(実際の面接を何回もこなすのが重要であることは理解しています)
以下は、よくある5つの原因です。
- 自分で用意した回答に納得していない
- 準備の方向性があっていない
- 緊張してしまい言葉が飛んでしまう
- 面接官が求める回答を理解できていない
- 話しているうちにズレていってしまう
なぜ面接官とうまくコミュニケーションが取れなかったのかを振り返ると、原因や練習方法が見えてくるかもしれません。
以下のような練習方法がおすすめです。
- openAIなどで面接をお願いする
- 企業からフィードバックをもらう
- マインドマップなどを活用し、筋道を立てて言語化をする
- 面接官と対峙している状態を想像する(脳内シミュレーション)
- 質問を理解しているか、日常生活でも常に意識して会話をしてみる
- 話が長くなりがちな場合は、1分以内に収まるよう意識する
- 質問された内容を自分の言葉で繰り返してから答える
面接がうまくいかなかったときには、ただ繰り返し練習をするのではなく「なぜ話せなかったのか」「どこで詰まったのか」を振り返ってみることが大切です。
面接本番を想定したシミュレーションや、言語化の整理方法を取り入れることで、準備の進め方を自分なりに見直すヒントが得られるかもしれません。
他責に聞こえない転職理由の伝え方
転職理由を話すときに「前の職場への不満だと思われないか」「他責に聞こえてしまわないか」と不安を感じる人は多いのではないでしょうか。
キャリエモンQ&Aにも「他責に聞こえないかチェックしてほしい」という相談が寄せられていました。
【例文】
転職活動の軸は「適切な段階で成長できる環境に身を置く」ことが出来ることです。
現職では入社して間もないタイミングで、大型の案件にメインで担当させて頂くことが何度かありました。
案件進行にあたって重要な「関係者と認識を擦り合わせるコミュニケーション力」や「他業務と並行して案件を進めるマルチタスク力」といったスキルを磨くことができ、とても有意義な経験をさせて頂いたと感じています。
ただ、お客様からお預かりしたお金に見合うサポートをするためには自身の経験や知識が足りないと感じることもありました。
そのため、基礎的な知識や経験をしっかり積むことで、自信を持ってお客様の対応がしたいと考えています。
現在独学で進めているマーケティングの学びを並行しながらWebディレクションに関する実地の経験を積むことで、クライアントとの強い信頼関係を持つWebディレクターになりたいと考えています。
そして、いずれ出来るであろう後輩にも自信を持って案件に取り組めるよう段階を踏んで成長できる環境を作る一員になりたいです。
そのためにも、実地での経験を踏まえ部下の成長を見守ることを体現されている方の考え方や働き方に触れながら働きたいと考えています。
「大型案件でスキルを磨いた有意義な経験を得られた」ことを述べたうえで、
「さらに知識や経験を積みたい」という前向きな理由を転職の動機として語っています。
転職理由として納得感のある構成です。
そのうえで、表現をさらにブラッシュアップするポイントとして2点をアドバイスされています。
| アドバイザーのアドバイス | 言い換えの例 |
|---|---|
| 企業と共通認識を持ちやすい表現にする | 適切な段階で成長できる環境に身を置く ↓ ・キャリアップの制度が充実している ・評価制度が明確 ・キャリアアップの選択肢が豊富 |
| Webディレクターになったあと、どんなことをしたいかまで伝える | クライアントとの強い信頼関係を持つWebディレクターになりたいと考えています ↓ クライアントと強い信頼関係を持つWebディレクターとして顧客のニーズを的確に反映したコンテンツを企画提案をしたいと思います |
このように、企業とのずれを防ぐために表現を少し言い換えたり、自分の思いをもう一歩深めて言葉にしていくことで、より伝わりやすくなります。
志望動機に一貫性を持たせる
転職活動では「なぜ辞めたのか」「なぜこの職種・この企業を選んだのか」をセットで問われる場面が多くあります。
その際、転職理由と志望動機に一貫性があるかどうかは、採用担当者があなたのキャリア観や入社意欲を測るうえで、最も重視するポイントのひとつです。
キャリエモンQ&Aに寄せられた実際の相談をもとに、一貫性をもたせて伝えるためのヒントを整理していきます。
【例文】
現在、金融機関にて窓口業務を担当しています。退職理由は、仕事において専門性を高めることで活躍していきたいと考えたからです。
現職では、銀行業務検定を受験し、財務や法務、税務などの知識習得に務めていまが、習得した知識を仕事上で実践する機会があまりありません。(金融商品の商品知識を深めることでお客様に提案できることはあります)
私自身、自分の能力を高めることで、チームに貢献したり周囲の役に立つことにやりがいや達成感を感じるので、仕事において専門性を高めることで会社やひいては社会の役に立ちたいと考えたため転職を考えました。
その中でも、これまで培った正確な事務処理の力や知識(簿記3級や銀行業務検定ではありますが財務3級など)を活かせるのではないかという点と会社の経営状態を把握、企業の経営を下支えすることができる経理事務に興味を持ちました。
退職理由と経理を目指す方向性に一貫性がある内容になっています。
一貫性をより強めていくために、経理として活躍するために現在努力していることを追加するのがおすすめです。
例えば「簿記2級の取得に向けて毎日勉強していて、⚪︎月に取得予定です」などの情報を伝えることで、本気で目指していることが伝わりやすくなります。
現職で感じた課題や学びを、転職理由として整理し、その延長にある職種や企業でどう活かしたいのかを伝えることで、志望動機には一貫性と説得力が生まれます。
就活と転職活動を両立しながら書類選考を突破するための工夫
就活と転職活動を両立させる中で書類選考を通過するには、自分の強みや志望理由でアピールできるよう表現を工夫することが欠かせません。
エントリーシートや履歴書では、内容そのものに説得力があるかはもちろん、読み手に「自分らしさ」や「企業とのマッチ度」を伝えられているかどうかが問われます。
この記事では、キャリエモンQ&Aに寄せられた実際の相談をもとに、書類選考を突破するために意識したい3つのポイントを整理して紹介します。
- 具体的な内容を盛り込む
- 「その会社を志望する理由」を述べる
- 他の就活生と差別化を意識する
1.具体的な内容を盛り込む
書類選考を突破するためには、自己PRや志望動機に具体的なエピソードや行動の裏付けを盛り込むことがポイントです。
キャリエモンQ&Aにも「自己PRでどの部分を詳しく書くべきか」などの相談が寄せられていました。
【例文】
アルバイト先で3年連続交流会の幹事を務め、最終年は100名規模のイベントの代表を担当しました。
前年には機材トラブルや予算不足に直面し、原因は役割分担の不明確さにあると分析。
そこで翌年は、メモアプリでの情報共有、メンバーの強みを活かした分担、定期的な進捗確認など、チーム全体の見える化と連携強化に取り組みました。
その結果、イベントはトラブルなくスムーズに進行し、「過去一番よかった」といった声を多数いただくことができました。
以下の点で具体的な内容を盛り込むことを考えてみましょう。
- 「役割分担の不明確さ」とは、具体的にどのようなことか
- メモアプリでの情報共有/メンバーの強みを活かした分担/定期的な進捗確認を具体的に記載する
- 「過去一番よかった」は「売上、効率、満足度、困難度、貢献度」など、どの側面で「一番」だったのかを具体的にする
- 交流会の対象/プレゼントの経緯と対象を追記する
読み手に伝わりやすくするために、何を・どのように・なぜ書くかを意識することが、書類選考を突破するうえで重要だといえます。
実際の経験を、どんな課題があり、どんな工夫をし、どんな成果があったのかまで具体的に言語化することで、内容に信頼性と説得力が生まれます。
読み手が自然に状況をイメージできるように書くことが、自己PRを「伝わる言葉」に整える第一歩です。
2.「その会社を志望する理由」を述べる
書類選考で重視される志望理由欄では「なぜこの会社なのか」「なぜこの職種なのか」を、志望企業に応じて具体的に言語化することが求められます。
キャリエモンQ&Aには、志望動機について、職種や企業に合った内容になっているかをアドバイスしてほしいという相談が寄せられていました。
【例文】
私は「ITを活用して社会の課題を解決する」仕事に挑戦したいと思い、貴社を志望いたしました。
大学のゼミで全国の選挙公報の分析を行なった際、多くの情報を収集・整理して意義のある結論を導き出す過程にやりがいを感じました。
この経験を活かし、御社の多様な業界向けシステム開発を通じ、社会課題の解決に取り組みたいと考えています。特に、エンタープライズ系や組込み系開発は顧客ごとに異なるニーズを捉え、柔軟に対応する必要がある分、大変さも伴う仕事だと認識しています。
しかし、そのような環境で経験を積むことで、自分を成長させ、最適な解決策を提供できる人材として貢献したいと思います。また、貴社の独立系企業ならではの幅広い分野での活躍に魅力を感じています。
そこで得られる多様な経験を通じてスキルを磨き、貴社とともに社会のより良い未来を実現していきたいです。
以下は、実際の回答をもとに志望動機作成において重視されるポイントとその説明を整理したものです。
| 追記内容 | 理由・詳細なポイント |
|---|---|
| 企業への貢献意欲と活躍可能性 | 伝えた結果「この人を採用すればうちの会社で活躍してくれそうだな!」と感じてもらえるような伝え方をすることが大切 |
| 志望のきっかけ(過去の経験) | 以下の2点で活躍してくれそうかを伝えやすい ・志望するようになったきっかけ(過去の経験) ・しっかりと職種理解(入社後ミスマッチをしないか)をしているか |
| 職種理解 | せっかく優秀な方を採用しても、想像している働き方と実際の働き方にギャップがあり、辞めてしまうと、ご相談者と採用する企業の双方にとってデメリットとなってしまう |
志望動機では「この会社に入りたい」という気持ちを伝えて「入社後の働き方がイメージできているか」「企業との相性が良さそうか」を判断されます。
今回のように、自分の経験や関心と企業が求める人物像を照らし合わせながら、職種理解や実際の取り組みを通じて一貫性のある動機を言語化することが大切です。
詳しい添削内容やアドバイスの詳細は、Q&Aをご覧ください。
3.他の就活生と差別化を意識する
ガクチカやエピソード記述を通じて書類選考を突破するには「よくある経験」でも「伝え方」によって大きな差が生まれます。
だからこそ、自分ならではの視点や工夫、行動の背景をどう伝えるかが、差別化のカギになります。
キャリエモンQ&Aには、以下のような相談が寄せられました。
【例文】
サッカーサークルの代表として【全員が心から楽しめる場】の提供に挑戦した。
私は、コロナ禍で思い出作りの機会が減少したからこそ、大学生活を振り返った時に「楽しかった」と心から思える瞬間を仲間全員に届けたいと考えた。
だが、代表就任時の活動参加率は20%と低迷し、活気もなく、心から楽しめる場ではなかった。
そこで全員と面談し、目指す姿や想いを把握した。そして誰一人取り残さないことを軸に、3つの施策で参加率と活気の向上を目指した。
①ターゲット別の活動や交流会などの多様な企画を展開。
②復帰組に対して参加ハードルを下げる呼び込み策。
③企画実施後のアンケート調査で企画内容の改善。
その結果、参加率は60%となり、活動に活気が戻った。また仲間から「良い思い出になった」という声を聞き、心から楽しめる場の提供を達成できたと実感した。
この経験から多様な価値観を束ね、皆を巻き込みながら価値を提供する力を磨く力を養った。
相手視点に立った読みやすい、他の就活生と差別化できる表現を目指しています。
読み手が「この人だからこそできた経験」だと感じられるようにするためには、自分自身の言葉で伝える工夫が欠かせません。
以下、差別化を図るために意識するポイントをまとめました。
| 定量的な表現の強化 | 「活動参加率は20%」といった表現に加え、全体の人数を明記する |
|---|---|
| 課題認識の具体化 | サークルの活動における具体的な課題は何だったのか、なぜその課題を解決する必要があったのかを明確にする |
| 施策内容の具体化と独自性 | 相談者が挙げた施策を具体的に記載し、独自の取り組みであることをアピールする |
| 経験から得た学びの汎用性 | 経験から得た学びを自分自身の言葉でより具体的に言語化し、その学びが他の場面(入社後)でも活かせる汎用的なスキルであることを示す |
| 成果の持続性 | 参加率向上や活気が戻った結果、サークルがその後どのように変化したか、新たな活動につながったかなど、取り組みが持続的な影響を与えたことを示す |
他の就活生と差をつける自己PRは、特別な経験があるかどうかではなく、その経験をどう捉え、どう言語化するかにかかっています。
どんな経験も、相手視点に立って丁寧に言葉にしていけば、伝わり方は大きく変わります。
課題への向き合い方や工夫、そこから得た学びまでを丁寧に言葉にすることで、あなたらしさが伝わり、印象に残る自己PRにつながります。
納得できるキャリアチェンジを実現するためのヒント|就活・転職活動の両立視点
特に第二新卒のタイミングでは、社会人経験を積みながらも、自分にとって本当に納得できる仕事を選び直すチャンスでもあります。
一方で、行動に移すには不安や迷いがつきものです。
過去の経験や今の立場を活かして「これからどんな働き方をしていきたいのか」を整理することが、後悔のないキャリア選択につながります。
実際の相談をもとに、就活と転職の両立を意識したキャリアチェンジのヒントを一緒に探っていきます。
自分の「本当にやりたいこと」を見つける
「今の仕事に不満はないけれど、このままでいいのかな?」
そんな迷いを抱えながら、転職を検討する人も少なくありません。
特に20代のうちは選択肢が多く、どれを選ぶべきか迷って動けなくなる場面もあります。
だからこそ、これまでの経験や価値観を丁寧に振り返りながら、自分が納得できる進路を見つける姿勢が大切です。
キャリエモンQ&Aにも「今の会社で働き続けるべきか、それとも人と関わる仕事に転職すべきか」と悩む第二新卒の相談者から声が寄せられていました。
【相談内容】
私は情報通信建設業に就いています。業務内容は、設計を行っています。
しかし、私は人事など人に関わる仕事をしたいと思っています。また、コミュニケーション能力も洞察力を強みだと思っています。そのため、人と関わる仕事で力を発揮できると考えてます。
今の会社に全く不満等はないですが、自分がやりたいこととフィットしているとは思いません。
今後、社会保険労務士の資格を取得しようと考えています。来年までに取得を目標にがんばります。この資格を取得できれば、キャリアコンサルタントも取得しようと思ってます。
第二新卒という肩書きが2026年3月までであり、それまでに社労士を取得できていれば100点ですが、それまでには厳しいと考えます。
やはり、第二新卒という肩書きがあるうちに、転職した方がいいのでしょうか?
これらを踏まえ相談に乗っていただきたいです。
「本当にやりたいこと」は、最初から見えているとは限りません。
そのうえで、以下のようなポイントを考えてみてください。
- 未経験職への転職を検討している場合は、早めに経験を積むことが望ましい
- 人事を目指す場合は、営業経験がある方が採用されやすい傾向にあるため、営業職への転職を考えるのも選択肢のひとつ
- 第二新卒の定義は企業によって異なるため、現職での区切りや転職の目的をもとにタイミングを考える
- どんな仕事が向いているかは「将来どんな状態になっていたいか」から逆算して考えてみる
納得のいく選択をするためにも、これまでの経験を振り返り、自分がやりがいを感じた場面や、活かしたい強みを丁寧に言語化してみましょう。
将来どんな状態で働いていたいかという視点から逆算して考えることで、これから進む方向が少しずつ明確になっていきます。
たとえ今すぐ答えが出なくても、自分自身と向き合うプロセスこそが、納得できるキャリアの第一歩です。
自分に合った「新卒カード」の活用方法を考える
就職活動を続けるべきか、それとも一度就職してから本当にやりたい仕事を探すべきかという分岐点に立ったときに新卒カードをどう活かすかは、多くの人が悩むテーマです。
そのため、自分の気持ちやこれからの働き方を一度立ち止まって見つめ直すことが、後悔のない判断につながります。
キャリエモンQ&Aには、内定承諾後に就活を再開し、インフラエンジニアとしての仕事に迷いが生じた相談者からの声が寄せられていました。
【相談内容】
3月にエージェント様からご紹介いただいた企業様(エンジニア職・東京勤務)から内定をいただき、承諾しました。
しかし、待遇や給料よりもインフラエンジニアとして技術を磨ける企業を探したいと考え、就活を再開しました。特に、研修の充実度や上流工程から一連の開発フローに携われる環境を企業選びの軸としました。
2社で最終面接まで進みましたが、不合格でした。振り返ると、最終面接でその会社で働きたいという熱意を十分に伝えられず、準備にも熱が入らなかったように感じます。自分が本当にやりたい仕事なのかと思うようになりました。
再開した就活では、最終面接まで進んだ企業の選考を受けたら就活をやめようと考えていました。加えて、自身にモチベーション的にも就活を続けることに限界を感じています。
そこで、内定先に就職して本当にやりたい仕事を見つけてから転職するのが良いのか、それとも新卒カードを使って本当にやりたい仕事を見つけるまで就職活動を続けるべきか、双方のメリットデメリットもふまえて教えていただけると幸いです。
この場合、以下の視点で考えてみましょう。
- やりたいことが明確でない場合でも、できることを増やせば見つかる可能性が高まる
- 新卒のうちにやりたいことが見えていない人も多く、自分の適正や強みを活かせる分野にまずは全力を注ぐ
- まずは内定先で働くために勉強や準備に時間をあてる
- 「本当にやりたいこと」が見えていて、新卒でしか就職できない領域であれば、挑戦する価値はある
「新卒だからこうすべき」と一律に考えるのではなく、今の気持ちや将来像、強みとの接点を振り返ってみる姿勢が大切です。
その上で、自分なりに納得できる選択をすることが、新卒カードを活かすカギになります。
まとめ
就職活動と転職活動を両立させることは、決して簡単な道のりではありません。
まずは過去の経験や価値観を振り返りキャリアの方向性を見つけ、段階的なキャリアプランを描くことが大切です 。
また、面接でのコミュニケーション力向上や、ネガティブに聞こえない転職理由、一貫性のある志望動機を伝えるなど、伝え方の工夫も必要となります。
具体的な内容を盛り込み、企業への貢献意欲と活躍可能性を提示し、他の就活生と差別化を意識した応募書類を作成することがカギとなります。
「本当にやりたいことが見つからない」「応募書類の書き方が分からない」「面接でうまく話せない」といった悩みは、一人で抱え込む必要はありません。
キャリエモンQ&Aには、あなたと同じような悩みを抱える多くの就活生・転職希望者からの相談と、それに対するプロのアドバイスが豊富に寄せられています 。
キャリエモンでは、プロのキャリアサポーターがあなたのガクチカや自己PR、志望動機添削、キャリア相談全般などを無料でサポートしています 。
第三者の視点を取り入れ、客観的なアドバイスを受けることで、自分だけでは気づけない強みや改善点を発見し、質の高い応募書類の作成が可能です。
納得できるキャリアチェンジを実現するために、ぜひキャリエモンの無料キャリア相談を活用し、自信を持って選考に臨みましょう 。














