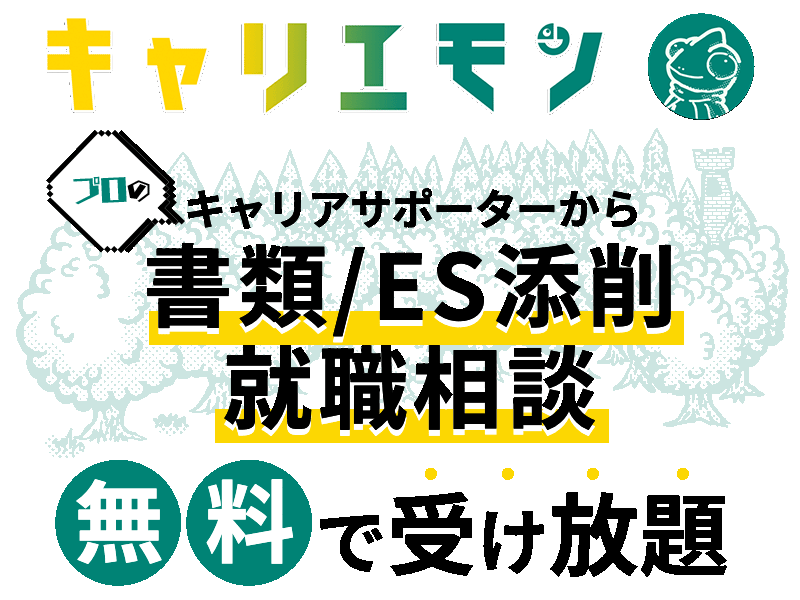人前での発表が苦手なのですが、どう改善すればよいでしょうか?|「挫折・苦労した経験」の相談
2026年3月に大学(学士)を卒業予定
22歳 女性
相談日: 2025年7月4日
1
1人のサポーターが回答
相談・質問の内容|人前での発表が苦手なのですが、どう改善すればよいでしょうか?
志望業界:
志望職種:
どんな観点でどんなサポートをしてほしいか:
大した挫折経験がないです。使える話か見ていただきたいです。
詳しい相談内容:
①大学のゼミでの発表は、私にとって大きな壁でした。人前で話すと声が震え、内容が飛んでしまうこともあり、「自分には向いていない」と感じることが多々ありました。実際、初めての発表では緊張からうまく話せず、悔しさと自己嫌悪を感じました。
しかし、逃げ続けたくないという思いから、自分なりに緊張を和らげる工夫を始めました。原稿を話し言葉に直して音読を繰り返したり、スマホで録音して聞き返すなど、一人での練習に力を入れました。また、「伝える」より「共有する」と意識することで、少しずつ発表への抵抗も和らぎました。
今でも得意とは言えませんが、「緊張してもやり切れる準備力と工夫」は身につきました。この経験を通して、苦手なことにも工夫を重ねて向き合えば、成長につながるという実感を得ました。
② 私が挫折を感じたのは、高校3年の文化祭準備で、クラス内に衝突が起きたときです。私は裏方として買い出しや予算管理を担当していましたが、演者側からは「あれが欲しい」「こんな衣装を使いたい」など要望ばかりが寄せられ、予算や準備の手間を無視した無理な指示が多く、両者の間に大きな溝ができていました。
当初は「勝手すぎる」「全然こっちの状況が分かっていない」と感じ、相手に対する不満ばかりが募っていましたが、このままでは準備が進まないと思い、「まずちゃんと聞いてみよう」と演者側のリーダーに声をかけました。話してみると、相手も台本作成や演出に追われながら必死で動いていたことを知り、「立場が違うだけで、目指しているものは同じだった」と気づくことができました。
この経験から、対立したときこそ相手の背景や事情を聞き、歩み寄る姿勢が大切だということを学びました。今でも、人と意見が食い違ったときには、先入観で判断せずまず話を聞くことを意識しています。
キャリエモンを使ってみよう
プロのキャリアサポーターからガクチカや自己PR添削・志望動機添削・キャリア相談全般などを無料で受け放題!

回答タイムライン(1)
人前での発表が苦手なのですが、どう改善すればよいでしょうか?
人前での発表が苦手なのですが、どう改善すればよいでしょうか?
- Yushi Kishi回答日: 2025年7月7日ご相談いただきありがとうございます。 「大した挫折経験がない」と感じる、そのお気持ちは非常によくわかります。多くの就活生が同じように悩んでいますが、まず一番にお伝えしたいのは、企業は「不幸話の自慢大会」を求めているわけではないということです。 企業が「挫折経験」を聞く本当の目的は、 ・課題に直面した時、どのように考え、行動するのか(課題解決能力) ・失敗から何を学び、次にどう活かすのか(学習能力・成長性) ・ストレスや困難な状況にどう向き合うか(ストレス耐性) を知るためです。 その観点から見ると、挙げてくださった2つのエピソードは、どちらも素晴らしい人柄や能力を示す、十分に「使える」素晴らしい経験です。 2つのエピソードの客観的な評価 どちらも良いエピソードですが、それぞれに長所と短所、そして適した場面があります。 ① ゼミの発表(苦手克服)のエピソード 良い点 ・大学での経験であり、時系列的に新しい。 ・主体的な課題解決力と地道な努力を継続できる力が伝わる。 ・「伝える」から「共有する」へ、という思考の転換ができており、内省の深さを示せている。 懸念点 ・物語が「個人」で完結しており、チームへの働きかけという要素が弱い。 ・「人前で話すのが苦手」という点が、職種によっては(例えば営業職など)、わずかに懸念として映る可能性もゼロではない。(※ただし、克服プロセスを語れているので大きな問題ではありません) ② 文化祭の衝突(対人関係の課題解決)のエピソード 良い点 ・より高度な対人能力を示せている。「自分の苦手克服」よりも、「チーム内の対立解消」の方が、ビジネスの現場で求められるスキルのレベルが高い。 ・共感力、傾聴力、調整力といった、総合職に不可欠な素養を一度にアピールできる。 ・「立場が違うだけで、目指すものは同じ」という気づきは、非常に素晴らしい視点であり、高く評価される。 懸念点 ・高校時代の経験であること。これが唯一にして最大の懸念点です。採用担当者によっては「大学時代に、チームで何かを乗り越えた経験はないのだろうか?」と感じる可能性があります。 【結論】どちらを、どう使うべきか 私としては、②の「文化祭」のエピソードをメインに使うことを強くお勧めします。 なぜなら、このエピソードで示されている「立場の違う相手の背景を理解し、合意形成を図る力」は、社内外の多くの人と関わる総合職の仕事において、最も重要かつ再現性の高いスキルだからです。①で示せる「個人の努力」よりも、②の「組織を動かす力」の方が、より高く評価されるでしょう。 ただし、「高校時代の経験である」という懸念点を払拭するための「語り方の工夫」が不可欠です。 ・ 対話の結果、どのような変化が起きたのか(前向きな議論への転換)を追記し、質問者様の働きかけの成果を明確にしましょう。 ・ 最後の文章で、「高校時代の学びが、大学生活や現在のアルバ・イトにおける行動指針になっている」と明確に語ることで、「過去の美談」ではなく、「現在の質問者様を形作っている、再現性のある強み」であることをアピールしましょう! これにより、「なぜ高校時代の話?」という懸念を払拭できます。 これらを踏まえて再構成してみてください! 質問者様の持つ、相手を理解しようとする誠実な姿勢は、素晴らしい強みです。応援しています!