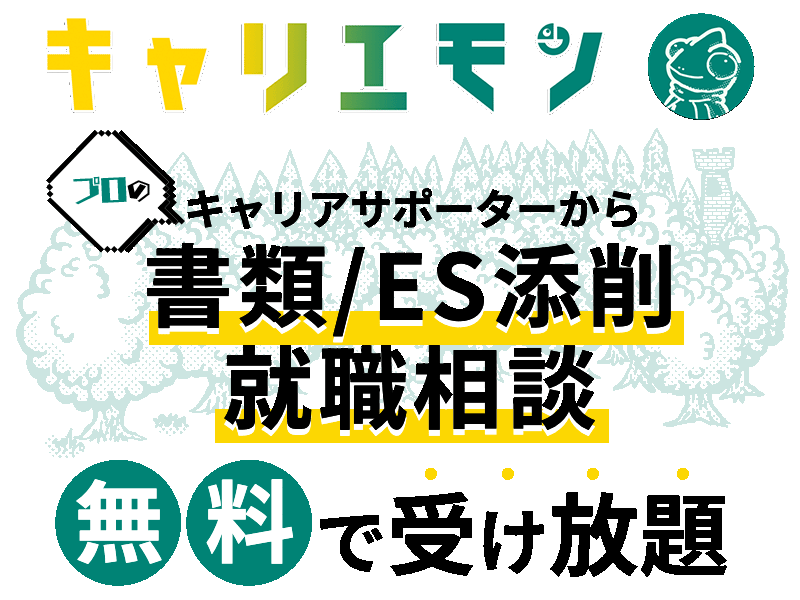現業職で苦手な年上の従業員とはどう接すればよいでしょうか?|「面接全般」の相談
2026年3月に大学(学士)を卒業予定
21歳 性別未回答
相談日: 2025年5月10日
10
4人のサポーターが回答
相談・質問の内容|現業職で苦手な年上の従業員とはどう接すればよいでしょうか?
志望業界:鉄道業界
志望職種:現業職
どんな観点でどんなサポートをしてほしいか:
詳しい相談内容:
苦手な人とはどう接するのか(現場編)?
私が苦手な人は人の意見に耳を傾けない人です。特に年上の従業員と一緒に働く際には、立場や年齢の関係でこちらの注意を素直に受け入れてもらえないこともありました。
私は先輩としてミスや改善点についてはできるだけ丁寧に伝えるようにしましたが、それでも状況が改善しない場合は店長に相談し、「○○さんはこういう傾向があるので店長からもフォローしていただけませんか」とフィードバックをお願いしました。
この経験から御社では職種間を超えてチームで業務を行うことになると思いますので、そうした人がいた際には周囲に相談しながらチームとして解決していくことが大切だと感じています。
やはり現場でお客様と直接接している以上、現場の人間が業務に支障をきたしてしまうとお客様にも影響してしまう可能性ありますので、現場の責任者として迅速に解決していく必要があると思い、周囲に協力を仰いできました。そうしたことで他の従業員は反省の姿勢が見られることもあり、店舗全体運営にも支障をきたすことなく、貢献できたと思います。
前にも「苦手な人はどんな人か?」という答え方に対してあげたかもしれませんが、今回は現場で起こりえるのに合わせて回答しました。
内容面で問題ないでしょうか?
キャリエモンを使ってみよう
プロのキャリアサポーターからガクチカや自己PR添削・志望動機添削・キャリア相談全般などを無料で受け放題!

回答タイムライン(10)
現業職で苦手な年上の従業員とはどう接すればよいでしょうか?
現業職で苦手な年上の従業員とはどう接すればよいでしょうか?
- Takaaki Kanehara回答日: 2025年5月11日ご相談ありがとうございます! 過去の経験に基づき具体的な対処法とそこからの学びを言語化されているので、わかりやすく伝わってきました! 内容としても、問題を1人で抱え込まずに、周囲に相談し、チームとして解決しようとする姿勢があるので良い回答だと思いました! いくつかアドバイスさせていただきますね^^ ①内容について 年上の従業員として働く際に苦労した、先輩としてミスを注意したとあるので、投稿者さんは、年下だけど先輩?という認識で合っていますか?面接官にも違和感を感じられるかもしれないので、実体験を話す際には「アルバイトで」といったことも入れると良いかと! ②表現の仕方について ・「先輩としてミスや改善点についてはできるだけ丁寧に伝えるようにしましたが、それでも状況が改善しない場合は店長に相談し、「○○さんはこういう傾向があるので店長からもフォローしていただけませんか」とフィードバックをお願いしました。」 →この表現が一方的に自分の意見を押し付けていると感じられるかもしれないです・・・ 事実だとしても、面接では「経験や考え方の違いから、こちらの意図がすぐに伝わらない難しさを感じることもありました」のように相手への配慮を含ませた表現にした方がいいと思います! ・「やはり現場でお客様と直接接している以上、現場の人間が業務に支障をきたしてしまうとお客様にも影響してしまう可能性ありますので、現場の責任者として迅速に解決していく必要があると思い、周囲に協力を仰いできました。そうしたことで他の従業員は反省の姿勢が見られることもあり、店舗全体運営にも支障をきたすことなく、貢献できたと思います。」 →この表現も注意したいです! 「他の従業員は反省の姿勢が見られることもあり」と言ってしまうと、面接では他責思考に捉えられてしまい面接官から厳しい目を向けられます。他の従業員のミスは自分の言い方、表現の仕方が悪かったというような内容(直接的には言わなくて大丈夫です)を伝える方が、会社に入っても客観的にみて行動してくれる人だと印象を残すことができます! ③文章の構成について 苦手な人の対応の仕方→実体験→会社での貢献の仕方→実体験 という順序になっているので揃えた方がわかりやすいです! 実体験を伝え切ってから会社での貢献の仕方を伝えられるとわかりやすい文章の構成になると思います! よかったら参考にしてみてくださいね! またいつでもキャリエモンで相談してください!
- 相談したユーザー返信日: 2025年5月11日フィードバックありがとうございます。 ①内容について 年上の従業員として働く際に苦労した、先輩としてミスを注意したとあるので、投稿者さんは、年下だけど先輩?という認識で合っていますか? →その内容で問題ございません。その時は私が年下であり、年上の後輩に指導をする立場でした。 2の表現の仕方に関しまして、模範解答異例を提示していただけると幸いです。 そうしたことで他の従業員は反省の姿勢が見られることもあり、店舗全体運営にも支障をきたすことなく、貢献できたと思います。」 →この表現は成果の部分として提示しましたが、他責思考ということで修正いたします。 何卒よろしくお願い申し上げます。
- 相談したユーザー返信日: 2025年5月12日重ねての質問になってしまい、申し訳ありませんが、「苦手な人はどんな人ですか」という回答に対して以下の内容はどうでしょうか? 以下は鉄道の現業職に完全に合わせたものになります。 また以下の内容は「これまでの人生で怒られた経験はありますか?またその経験を通して自身は変化したのか?」 という質問にも応用できると思います。 私の苦手な人は甲高い声を持つ人です。アルバイト先のローソンで非常に厳しく指導する先輩がおり、当初はその口調や態度に圧を感じ、苦手意識を持っていました。しかし実際に業務で収入印紙の貼り付けミス、住所入力のミス、チケットの渡し忘れ等ローソンの扱っているサービスではそういった一つでも抜けがあると後に大きなトラブルにつながってしまいます。またコンビニをご利用なさるお客様には年齢層や背景が幅広いため、レジでの対応が遅いだけでクレームに繋がってしまうこともあります。そうしたことから厳しさの裏にはトラブルやクレームを未然に防ぐという責任感があるのだと実感し、前向きに受け止めるようになりました。 御社に入って鉄道においても乗客に対する安全性や時間といった定時制など厳しい基準が求められる場面が多くあると思います。そのため上下関係の厳しさ、細かいミスでも厳しい指導や罵声を浴びられたり、特に乗務員においては反省文や懲罰を含む日勤教育が求められたりする点で大変だと思いますが、その背景には定時制や安全性が厳守されているという背景があるのだとくみ取っていき、お客様の命をお預かりしているという重みをもちながら公共の安全を守るという意識をもとに自身の業務パフォーマンスに励んでいくことを目指します。
- 佐野美七海回答日: 2025年5月12日ご相談頂きまして誠にありがとうございます! 少しでもお力になれればと思い横から失礼します>< 私からも少しアドバイスをさせて頂きますね✨ ◾️文章全体の印象に関して 現状の文章ですと、「苦手な人はどんな人ですか」に対しての回答というより、「これまでの人生で怒られた経験はありますか?またその経験を通して自身は変化したのか?」に対する回答の方が納得感があります、、! なぜそう感じてしまうのか私なりに考えて見ましたので、下記2点にまとめました! ①苦手な人に対しての自分の考え方に関してのみの記載で、対応方法についての記載がない ②厳しい指導を題材にしてしまっている ①に関して 苦手な人を聞かれた時の回答方法として文章の構成は下記にて記載しましょう! 〈苦手な人の特徴→なぜ苦手なのか→それに対してどのように対処してどのような成果が出たのか→その経験から学んだことを活かして今後コミュニケーションをとる上で何を大切にしたいか〉 ②に関して 「非常に厳しく指導する先輩がおり、当初はその口調や態度に圧がある方」に対して苦手意識を持つのは非常に共感できます>< これを好む人は中々いないですよね、、! ただ気をつけて頂きたいのが、現状の伝え方だと他責思考が強い方だと思われてしまったり、ストレス耐性が弱いんだろうなと感じさせてしまう可能性が高く非常に勿体無いです! 他責思考を払拭するには、その後の対処方法や苦手だと感じる理由の部分に、 〈ミスをしてしまう自分(もしくは「 してしまう人」)に責任があるのは重々承知ですが、「威圧的に詰めていく」という方法は適切ではないと考えております。〉 のように自己反省に関する文章も入れたほうが印象が良いです!◎ ストレス耐性に関しては、「怒られたことが嫌だったんだろうな、うちの会社でも怒られたら辞めてしまうんだろうな」と思われてしまう可能性があると感じました>< そのため、そもそも冒頭の部分を「私の苦手な人は、人のミスに対して高圧的な態度で対処しようとする方です。」として、「厳しく指導されることに対しての苦手意識ではない」というのをアピールできると良さそうです! ◾️「甲高い声を持つ人」という表現に関して 結論から申し上げるとこちらの表現は避けた方が良いです。 声というのはその人の生まれ持ったものであり、単なる人格否定と思われてしまう可能性が高いので避けましょう>< 要所要所ポイントは掴めているので、細かい部分の修正をしてさらにブラッシュアップしていきましょう! 応援しております^^◎
- 丸山結希子回答日: 2025年5月12日ご自身の志望業界に合わせて作られたのは素晴らしいです✨ 苦手な人を聞かれるってなんだか心苦しいものではありますが、うまく面接官にアピールできるようアドバイスさせていただきますね! ■エピソードの具体化、言い回しを工夫しましょう! 「甲高い声を持つ人」と「非常に厳しく指導する先輩がおり、当初はその口調や態度に圧を感じ」のエピソードはイコールになっていないような気がします! 投稿者様が苦手意識を持つ人は、甲高い声の人か、口調や態度に圧を感じる人どちらでしょうか? 前者であればそこに繋がるエピソードを追記する、 後者であれば出だしを「私が苦手意識を感じる人は口調や態度に圧を感じる人です。」に変えても良いかもしれません◎ また「厳しく指導」に関しましても、こちらどんな点で厳しかったのでしょうか?記載いただいている通り口調や態度がきつく感じていたのでしょうか? 厳しく指導というのはやや抽象的な表現に感じるため、面接官に突っ込まれる可能性があります。 投稿者様が具体的にどういう部分が苦手だと感じたのか、エピソードをもう少し追記してみると、投稿者様の人柄を伝えられて説得力が増しますよ^^ ■苦手な人を聞く意図を理解し、自己PRに繋げましょう! 苦手な人を聞く意図としてはその人の人柄や性格、また会社に入って苦手な人がいた際どう関わっていくかを知りたいという目的があります。 今のままですと「コンビニアルバイトの大変さ」や「鉄道業界での大変さ」の説明をしているという印象が強く残ってしまう可能性があり、 投稿者様の良さや経験したことの内容が薄いため、勿体なく感じました! 「そのため上下関係の厳しさ、細かいミスでも厳しい指導や罵声を浴びられたり、特に乗務員においては反省文や懲罰を含む日勤教育が求められたりする点で大変だと思いますが」 こちらの文章も業界の厳しさを理解しているのは伝わってきますが、 併せて否定的な印象を持っているように感じ、面接官から「本当に入りたいのかな?」と思われてしまう可能性があります。 そのため上記の文章を省き、「御社に入って鉄道においても乗客に対する安全性や時間といった定時制など厳しい基準が求められる場面が多くあると思います。」のみでも十分に伝わると思います! プラスで、気持ちよく働くために対人関係の面で心がけたいことも追記できたらもっと良いです◎ 簡易的なものにはなりますが、下記例文となりますので参考になれば幸いです^^ 「私の苦手意識を感じる人は〇〇な人です。 そう感じたきっかけはアルバイト先での~~場面です。このことから意識したことは〇点あります。1つ目は~です。2つ目は~です。 そこで~の大切さを学びました。 御社では~~が求められると考えております。自分自身の意識してきたことを生かし、今後も~~できるよう努めてまいります。」 ■「これまでの人生で怒られた経験はありますか?またその経験を通して自身は変化したのか?」という質問 応用できると思います!その際も面接官が質問してくる意図を考え、投稿者様の良さや取り組みが最大限に伝わるよう書き方を工夫してみてくださいね✨ また不明点があった際はいつでもキャリエモンを頼ってくださいね^^◎ 応援しております✨
- 相談したユーザー返信日: 2025年5月12日お二方の丁寧なフィードバックありがとうございます。 それらのアドバイスを踏まえた上で以下の内容に修正いたしました。 私が苦手意識を感じる人は口調や態度に圧を感じる人です。そう感じたきっかけは以前アルバイト先のコンビニで非常の厳しい先輩と一緒に働いていた経験があります。そのときは少しのミスでも強い口調で指導し、その態度に萎縮することがあり、話しかけづらいと感じていました。例えばチケットの渡し忘れや収入印紙の貼り付けミスなどが後々どれだけ大きなトラブルにつながるのか想像してみて」と強く注意を受けました。そのときにコンビニの業務は細かい確認の積み重ねで成り立っており、一つ一つの作業に大きな責任があることを実感しました。またお客様の年齢層や背景が幅広く、少しの対応の遅れがクレームにつながるということからその面でおつりの渡し方などにも細かく指摘されたこともあります。 この経験から先輩の厳しさは感情ではなく、ミスによるトラブルを未然に防ぐという責任感の表れだと受け止められるようになりました。そして単に苦手意識を持つのではなくその指導の仕方がなぜ必要かを学ぶ大切さも実感しました。 御社に入って鉄道においても乗客に対する安全性や時間といった定時制など厳しい基準が求められる場面が多くあると思います。そのため細かいミスが大きな影響を及ぼすことがあり、上下関係や時には厳しい指導を受ける場面があるかと思われます。しかしそれはその背景にある定時制や安全性といった責任や使命感があるのだと理解し、自身の感情だけでなく、合理的に受け止めていき、自身の業務パフォーマンスを高めていくことを目指します。 いかがでしょうか?
- 相談したユーザー返信日: 2025年5月12日もしくは鉄道業界において苦手な人の切り口として「口調や態度に圧を感じる人」というのは地雷を踏んでしまうのでしょうか? もしその場合は別の切り口に検討しようと思っております。 面接では申し上げませんが鉄道業界のリアルな一面ですと 上下関係の厳しさ、細かいミスでも厳しい指導や罵声を浴びられたり、特に乗務員においては反省文や懲罰を含む日勤教育が求められたりする点 は定時や安全性を厳守する上でどうしても必要不可欠だと思いますので、もしかしたら実際の駅長や現場クラスの社員からすると差し支えるのではと私は思っております。 切り口は変えた方がよろしいかどうか、重ねての質問になってしまいますが、ご返信いただけると幸いです。
- 丸山結希子回答日: 2025年5月13日早速修正いただいてありがとうございます! アドバイスをすぐ行動に移す姿勢はとっても素晴らしいです✨ より良くなるようアドバイスさせていただきますね◎ ■表現の仕方や簡潔な文章を意識しましょう! ・「非常の厳しい先輩と一緒に働いていた経験があります」 「非常に厳しい」に関しては前述でもあげているように、抽象的な表現になってしまうのと、文頭に記載していただいている「口調や態度に圧を感じる人」と表現がずれてしまいます。 そのあとにエピソードを書いていただいているので、省いて下記の文章に書き換えてみてもいいかもしれません! 「そう感じたきっかけは、以前働いていたコンビニのアルバイトで、自身のミスに対して指摘があった際に感じました。」 ・「少しのミスでも強い口調で指導し~」 この後に「チケットの渡し忘れや収入印紙の貼り付けミス」と具体的に記載いただいているので、下記のようにくっつけてしまってもいいかと思います! 「チケットの渡し忘れや収入印紙の貼り付けミスをしてしまった際に、高圧的な口調で指導され、委縮し話しかけづらいと感じてしまいました」 ・「ミスによるトラブルを未然に防ぐという責任感の表れ」 責任感の表れというのが少し上から目線に感じてしまうのと、「元々責任感持ってなかったの?」と思われてしまう可能性が高いです。 ここは簡潔に伝えるくらいで問題ないと思うので、 「ミスによるトラブルを未然に防ぐために必要な厳しさであったと受け止めることができました」というような文章に書き換えてみるのはいかがでしょうか? ■受け身ではなく主体的な行動を記載するようにしましょう! 今後の取り組みとして業界に合わせて書かれているのはつながりがあって分かりやすいです◎ 「理解」や「受け止める」など投稿者様の受け取り方を意識する取り組みは書いてくださっておりますが、それだけですとやや受け身なように感じます! 苦手な人に対して、どのようにコミュニケーションを取って関わっていくか主体的な取り組みがあると、他責志向ではなく前向きに捉えられているな!と好評価になると思います^^✨ ■鉄道業界において苦手な人の切り口として「口調や態度に圧を感じる人」というのは地雷を踏んでしまうのでしょうか? 結論で言うと、変えなくていいと思います! 細かいミスに対しての厳しい指導や高圧的な態度な方は業界業種に関わらずどこにでもあります。 また志望業界に合わせて回答を作りすぎても、自分自身の言葉で伝えられず説得力がなくなってしまうので、そのままでいきましょう◎ 苦手な人や場面に直面した際にどう対応していくかが面接官が最も知りたいことなので、 そこの部分をしっかりと伝えられれば「この人ならうちの会社でもやっていってくれそう」と印象付けられますよ^^ また不明点がありましたらいつでも仰ってくださいね!応援しております□
- 相談したユーザー返信日: 2025年5月15日返信が遅くなり、大変申し訳ありません。 以下のように修正いたしました。 私が苦手意識を感じる人は口調や態度に圧を感じる人です。そう感じたきっかけは、以前働いていたコンビニのアルバイトで、自身のミスに対して指摘があった際に感じました。チケットの渡し忘れや収入印紙の貼り付けミスをしてしまった際に、高圧的な口調で指導され、委縮し話しかけづらいと感じてしまいました。そのときにコンビニの業務は細かい確認の積み重ねで成り立っており、一つ一つの作業に大きな責任があることを実感しました。またお客様の年齢層や背景が幅広く、少しの対応の遅れがクレームにつながるということからその面でおつりの渡し方などにも細かく指摘されたこともあります。 この経験から先輩の厳しさは感情ではなく、ミスによるトラブルを未然に防ぐために必要な厳しさであったという点で単に苦手意識を持つのではなくその指導の仕方がなぜ必要かを学ぶ大切さも実感しました。御社に入って鉄道においても乗客に対する安全性や時間といった定時制など厳しい基準が求められる場面が多くあると思います。そのため細かいミスが大きな影響を及ぼすことがあり、上下関係や時には厳しい指導を受ける場面があるかと思われます。それはその背景にある定時制や安全性といった責任や使命感があるのだと理解し、自身の業務パフオーマンスを高めていきたいと思います。 このような形に修正いたしました。いかがでしょうか?
- 小久保桃佳回答日: 2025年5月16日横から失礼します! 丸山に代わり回答させて頂きますね! ■内容に関してではありませんが、しっかり内容を書けているが故に、少し一文が長い印象です! 句読点をしっかり使用して、読み手が読みやすいように工夫しましょう◎ ■そのため細かいミスが大きな影響を及ぼすことがあり、上下関係や時には厳しい指導を受ける場面があるかと思われます。 →書かれている内容から、入社後に厳しい場面があることを理解し、それでも前向きに取り組む姿勢が伝わってくる一文ですね! しかし、「上下関係や時には厳しい指導を受ける場面があるかと思われます」という表現は、人事の方に「うちの会社はそんなに厳しくてギスギスしているイメージを持たれているのか?」と思わせてしまうリスクがあります・・! 伝えたい核は「貴社の業務(特に鉄道の安全性や定時性)には高い責任が伴い、そのため品質管理やミスの撲滅が重要であり、厳しい基準やフィードバックがあることは理解している。その厳しさを感情的なものではなく、プロとしての責任感からくるものと捉え、自身の成長や業務改善に繋げたい」ということだと思います💡 この核を、会社側の厳しい側面を強調するのではなく、質問者様が「高い基準」や「責任の重さ」を理解しており、それに対してプロとしてどのように向き合い、成長していくかというポジティブな姿勢として伝えるようにしましょう! 少し難しい表現になってしまったので、一例を記載させて頂きますね◎ (例)時に厳しくも的確な指導やフィードバックが必要とされる環境があることも想像しております。私はコンビニでの経験から、責任ある仕事において、問題点を曖昧にせず、厳しくも建設的な指摘を受け止めることの重要性を学びました。この学びを活かし、、、、、などです! 長々と記載してしまいましたが、少しでも参考になれば幸いです! 微力ながら応援しております🌸