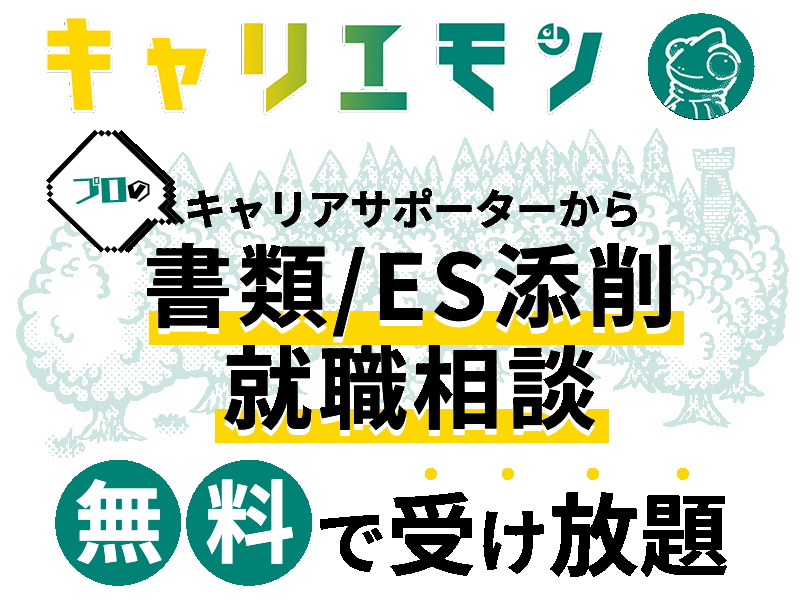成績アップの秘訣!私の挑戦と工夫|「ガクチカ」の相談
--歳 性別未回答
相談日: 2022年10月21日
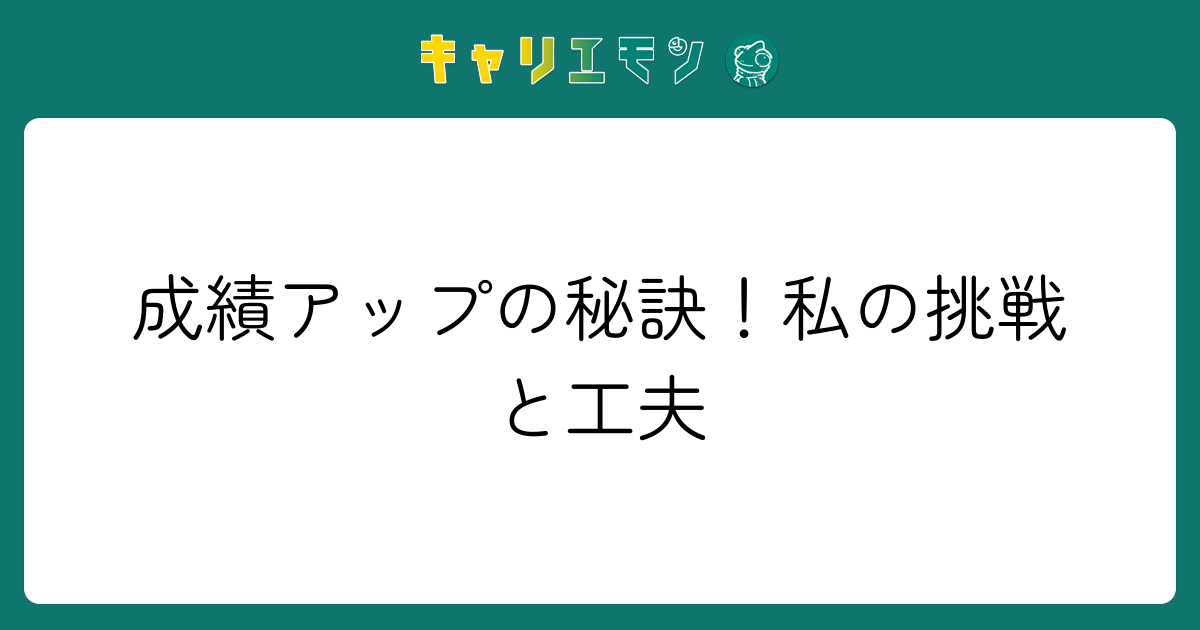
3
1人のサポーターが回答
相談・質問の内容|成績アップの秘訣!私の挑戦と工夫
ガクチカ2点の添削をお願いいたします。
志望:製薬業界(開発職、安全性管理職)・医療系出版社(編集職)・医療系IT
専攻:理学部(学部)⇒医学研究科薬理学教室(大学院)
以下2点に関してコメントを頂けましたら幸いです。
*自分の強み「課題に対して工夫しながら果敢に挑戦する力」をアピールできる内容にしたい。
*600字を作成するために加筆すべき部分を知りたい。
【ガクチカ➀】
2年間勤務した個別指導塾で担当生徒5名全員の試験成績向上に貢献した。授業に集中するのが苦手な小中学生を担当する中で、連発するミスに落胆し挑戦心が削がれる事が集中力低下の一因だと考えた。この状況に対し2段階の対策を講じ、生徒の成績向上を目指した。1段階目として『生徒の努力面を褒める』ことに注力した。字の丁寧さや途中式の書き方など、取組みの過程と変化に着目し授業中に必ず10回以上褒める事を心掛けた。努力面を積極的に保護者へ共有し、他の教員にも該当生徒の取組を褒める声掛けを依頼した。家庭と塾の双方向から生徒を支援する環境を目指し、生徒の学習意欲を刺激した。主体的に取り組むよう変化した生徒に『苦手分野の追加課題を課す』という2段階目の取組を実施した。勤務初日と比較して、生徒が問題を途中で投げ出さず解を導く過程に集中して取り組めるようになった。苦手分野にも臆せず挑戦する姿勢が定着した結果、担当生徒5名全員が定期考査で初めて平均点以上を獲得できた。(424)
【ガクチカ➁】
個人経営のタイ料理店で1年間働き、4名のリピーター獲得に貢献した。全15席ほどの小さな店舗で、調理作業補助と接客業務に携わった。「飲食店業務を通じて対人スキル向上に挑戦したい」という熱意が店長に伝わり、コロナ禍の厳しい経営状況にもかかわらず未経験者の私を雇用して頂けた。地元の常連が顧客の約6割を占める状況下で新規客の再訪を促進すべく、少しでも売上に貢献するため2つの取組を実施した。1つ目は『テイクアウトメニューの宣伝』である。接客を通して当メニューの存在を知る顧客が少ない事に気づき、店内ポスター掲示と新規客に対する退店時の宣伝を提案した。2つ目は『顧客の好みに応じたお薦めメニューの提案』である。注文時に顧客の辛さ耐性についてヒアリングし、辛さが苦手な新規客に対しては低刺激な料理を、本場の味を求める顧客には本格派料理を提案した。テイクアウトの認知度向上と丁寧なヒアリングが功を奏し、4名のリピーターを獲得した。(409)
キャリエモンを使ってみよう
プロのキャリアサポーターからガクチカや自己PR添削・志望動機添削・キャリア相談全般などを無料で受け放題!

回答タイムライン(3)
成績アップの秘訣!私の挑戦と工夫
成績アップの秘訣!私の挑戦と工夫
- ヤギのさくらちゃん回答日: 2022年10月21日ご自身の背景やどのような観点で添削してほしいかといった情報が添えられており、とても添削しやすいです🌸 こういった質問のご様子からもすでに仕事で活躍できるであろう優秀さがよく伝わります🌹 質問者さんはご自身なりの答えを見つける能力がある方だと思いますので、 加筆すべき部分をみつけたり、よりご自身の強みの解像度を高くして明瞭にアピールできるようにいくつか質問させていただきます。 1. タイ料理店で働くきっかけとなった「対人スキルを向上したい」という思いはどのような出来事や考えが発端でしょうか? 2. 質の高い工夫と質の低い工夫とはどこに差があると思いますか? 3. 工夫ができない人が工夫できるようになるためにはどうしたらいいでしょうか? あるいは工夫できないままで良いのであればその理由を教えてください。 4. 果敢に挑戦するということは、失敗する可能性もあるということです。それでも果敢に挑戦することが大切だと思うのは何が理由でしょうか?
- 相談したユーザー返信日: 2022年10月28日ご返信いただき、ありがとうございます。 これまで考えた事のなかった質問ばかりだったので非常に悩みましたが、 自己分析の一環になっている感覚が得られました! 以下、回答を送付いたします。よろしくお願いします! 1. タイ料理店で働くきっかけとなった「対人スキルを向上したい」という思いはどのような出来事や考えが発端でしょうか? 大学1、2年次に個別指導塾の講師アルバイトを経験。先生ー生徒という関係性の中で、相手に寄り添うコミュニケーションの大切さを学んだ。4年次に研究室配属の関係で引っ越す。新天地でアルバイトを探すにあたり、①将来、社会で多様なバックグラウンドをもつ人々と意思疎通できる力を養いたい②講師アルバイトで培ったコミュニケーション力を一層強化したい、と考えた。そこで、幅広い年齢層の方達と関わる機会が多い「飲食店アルバイト」に挑戦しようと決めた。 2. 質の高い工夫と質の低い工夫とはどこに差があると思いますか? PDCAサイクルを回して常に「更新」していくかどうかで、工夫の質が変化すると考える。 【質が高い工夫】 うまくいかなかった場合⇒方法を見直す、結果を残せている人からコツを取り入れる うまくいった場合⇒どの工夫が貢献したのか考え、さらに強化できないか検討する 【質が低い工夫】 うまくいかなかった場合⇒とりあえず成果がでるまで継続してみる うまくいった場合⇒最善策だと捉えて継続する、よりよいパフォーマンスを追求しない 3. 工夫ができない人が工夫できるようになるためにはどうしたらいいでしょうか?あるいは工夫できないままで良いのであればその理由を教えてください。 周囲の有識者などからフィードバックやアドバイスを貰い、自分の仕事に反映させることから始める。工夫できない状態=工夫の仕方が分からない状態だと解釈した。最終的に自身で試行錯誤しながら成果をあげるためにも、まずは周囲にいる先輩や指導者のスキルや技を体得し「土台」をつくることが必要だと考える。 4. 果敢に挑戦するということは、失敗する可能性もあるということです。それでも果敢に挑戦することが大切だと思うのは何が理由でしょうか? 大学受験で挫折した経験から「果敢に挑戦する」ことの大切さを知った。 地元一の進学校である高校に進学した私は、理系科目が大の苦手であったが生物を学びたい一心で理系を専攻した。成績が伸び悩み、進級するにつれて優秀な友人達と比較し強い劣等感を抱くようになった。勉強法や進路に関する相談を周囲にしようとも思わなくなり、1人で自習室に籠る時間が増えた。今振り返ると、独りよがりな努力であった。十分に対策できず、第一志望校に不合格となる。 「成果を出せる努力」を重ねなければと思い、一浪中に通った予備校では講師に毎日欠かさず質問する事を目標にした。周囲からフィードバックを貰うことで自身の課題が少しずつ明確になった。結果的に第一志望校には合格できなかったが、生命科学の教育制度が充実している大学に入学した。 大学では友人と一緒に勉強を教え合い、授業後すぐに教授の元へ向かい疑問を解消するよう心がけた。結果、学科80人中10位以内の成績を4年間キープすることができた。学部4年次には、K大学と提携している他大の研究室で卒業研究を行った。研究成果が出たことで、ゼミのメンバーでは唯一、学部4年の段階で全国規模の学会で発表することができた。 受験失敗の悔しさをエネルギーに変え、挑戦し続けたからこそ出会えた大学・研究室で貴重な経験を積むことができた。したがって、失敗を成長の糧にするためにも、「果敢に挑戦する」ことが大切だと考える。
- ヤギのさくらちゃん回答日: 2022年10月28日簡単ではない質問にも関わらず、よく考えてくださいました🌸 短絡的にスピードだけ重視するのではなく、悩みながら時間をかけてでもじっくり自分が納得できる回答を考え続けられる能力は非常に貴重です。 製薬業界の開発職などにはとてもよくマッチするのではないかと思います💯 内容もすてきですね! 質問者さんの人となりが伝わってくるいい内容です。 「果敢に挑戦する」の話に出てくる「成果を出せる努力」が「質の高い工夫」とも繋がっており、質問者さんの価値観を形成する土壌になるような重要なポイントなのだと思いました。 おそらく質問者さんの中で最初のガクチカに追記したいところが見えてきたり、別の切り口で書き直したい気持ちがでてきていると思います。 一度応募先を試しに1つ具体的に設定してみて、その応募先に向けた内容で、最初のガクチカを工夫して更新したものを1つ作ってみるのはいかがでしょうか? 投稿していただければ改めて添削いたします🌷