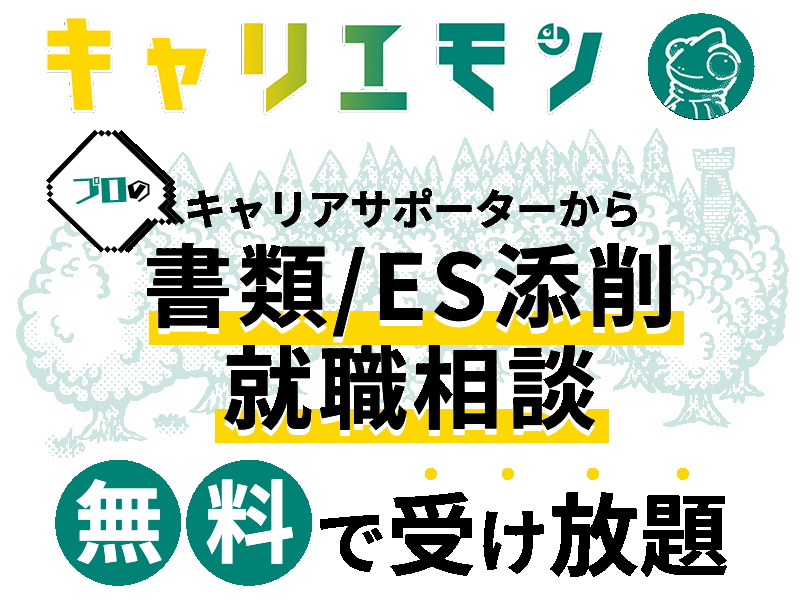大学で単位落とし…立ち直り方教えます!|「挫折・苦労した経験」の相談
--歳 性別未回答
相談日: 2022年4月11日
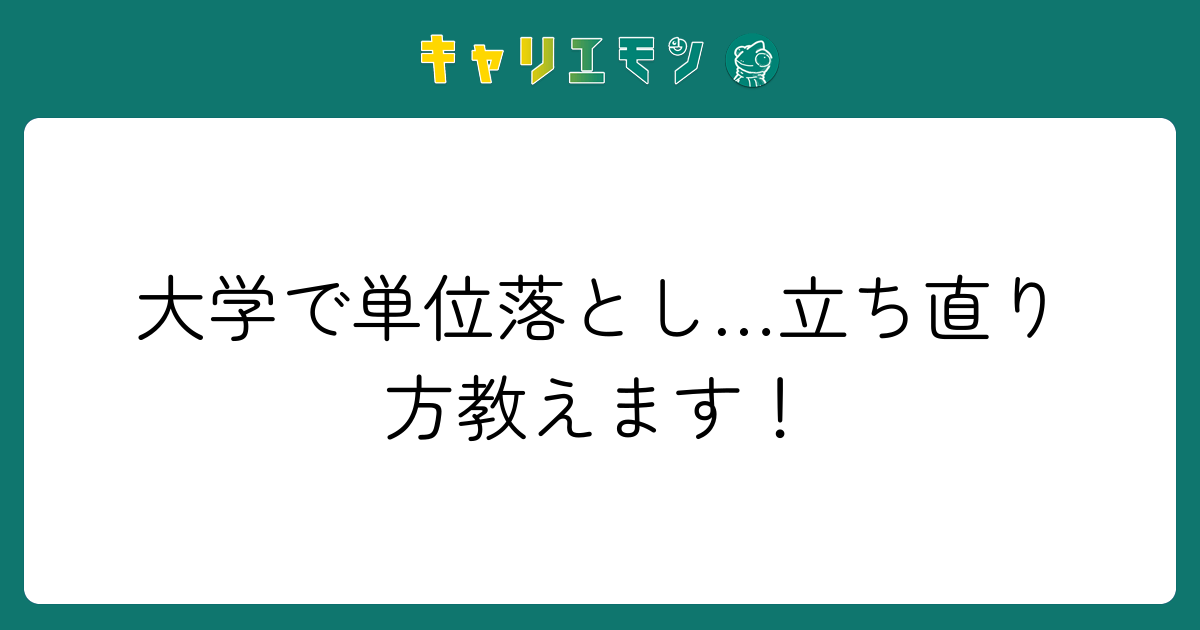
6
1人のサポーターが回答
相談・質問の内容|大学で単位落とし…立ち直り方教えます!
挫折経験の添削をお願いします。事務職を希望しています。
私の挫折経験は大学一年生の時です。私は一年生の終了時点で4単位も落としてしまいました。私は大学4年間で一度も単位を落とさずに卒業したいと考えていたので、これはとてもショックな出来事でした。一年生のうちはそんなに難しくないと聞いていたので、一年生のうちからこんな調子で本当に大丈夫なのかと、とても不安でした。このままではダメだと思い、何が原因なのかを自分なりに考え、二年生以降に対策しようと思いました。単位の取れなかった原因は計画を立てずに勉強を始めてしまい、あまり手をつけられなっかた科目があった事でした。なので、二年生以降はテストの一ヶ月前に何をいつ勉強するかの計画表を作り、自分の理解度なども含めて日程を変更したりなどして対策した結果、二年生で一年生の時に落とした分の単位を補うことができ、三年生でも一つも単位を落とさずに一年間を終えることができました。
キャリエモンを使ってみよう
プロのキャリアサポーターからガクチカや自己PR添削・志望動機添削・キャリア相談全般などを無料で受け放題!

回答タイムライン(6)
大学で単位落とし…立ち直り方教えます!
大学で単位落とし…立ち直り方教えます!
- (株)UZUZ代表取締役 岡本啓毅回答日: 2022年4月12日挫折経験を聞く面接官の質問の意図としては「仕事で大きな壁にぶつかったときに、めげずに乗り越えらる人だろうか?」と知りたくて聞いているためです。 そう考えると「単位を落としたことが1番挫折経験ということは、ちょっとしたことでも落ち込んでしまうんじゃないかな...」と心配されてしまうかもしれないな、と感じました。 また、挫折経験の質問の回答では「今まで試行錯誤して乗り越えた中で一番大きな成功を教えてください」と質問されていると思って回答すると良いです。そう考えると「2年、3年で単位を落とさなかった」という成果は少し弱いように感じました。 1番の成功体験となるエピソードを思い返して、それを乗り越える過程を挫折経験として伝えると良いと感じました。
- 相談したユーザー返信日: 2022年4月12日アドバイスをもとに考え直してみました! 私の挫折経験はmos wordに資格取得の際にモチベーションが上がらず、一度投げ出してしまったことです。オンライン授業のためレポート課題が課されることが多く、その際にwordを利用していたので資格取得に向け勉強を始めました。最初はモチベーションが高く、問題なく勉強できていたのですが、アルバイトと大学の授業や課題の合間をぬって勉強していため、やる気が起きずできない日が多くなり、モチベーションが低下して一度投げ出してしまいました。しかし、一度初めたことは最後までやり抜きたいと思い、少しだけでも毎日勉強するようにしました。すると無理のない範囲で地道に行うことによってモチベーションが上がり、結果として資格を取得することができました。この経験を活かし、御社でも地道にコツコツと業務に取り組み、事務職として会社しっかりサポートしていきたいです。
- (株)UZUZ代表取締役 岡本啓毅回答日: 2022年4月12日mos wordの資格はスペシャリストの合格率は約80%、エキスパートの合格率は約60%と難易度的にはそこまで高くない資格だったりするので、その資格を取ったことを伝えたとしても仕事での活躍イメージには繋がりづらいエピソードだと思います。 アルバイトの経験や、勉強面であればmosの資格という部分的な話ではなく学業全体を通じて「単位を落とさなかった」ではなく「好成績を収めた」などの別の切り口で成果を出したエピソードがあればそちらを選んぶと良いと思います。 また、「mos」と「単位を落とさなかった」で比較すると、単位を落とさなかったの方がどちらかと言えば良いエピソードだと思います。
- 相談したユーザー返信日: 2022年4月12日mosはやはり合格率が高いので弱いですよね。 学校の成績は3年生の数字はまだ出ていないのですが、2年生で学部全体2640人のうちの上位約25%の成績なのは好成績ではないですよね? GPAは4段階の3.14でした。
- (株)UZUZ代表取締役 岡本啓毅回答日: 2022年4月13日「mosに合格した」よりも、「単位を落としてしまっていた状態から、上位25%に入れるまでになった」という成果の方が何段階も良い成果だと思います!
- 相談したユーザー返信日: 2022年4月13日なるほど、とてもわかりやすかったです。 「単位を落としてしまっていた状態から、上位25%に入れるまでになった」という成果をもとに考え直してみます。