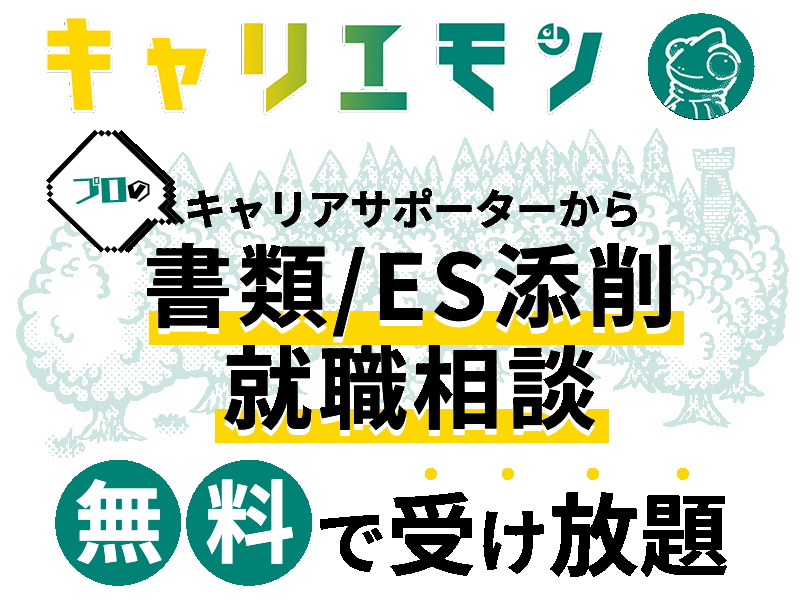就活初挑戦!私のES、どう思いますか?|「ES全般」の相談
2024年3月に大学院(修士)を卒業
26歳 男性
相談日: 2024年5月7日
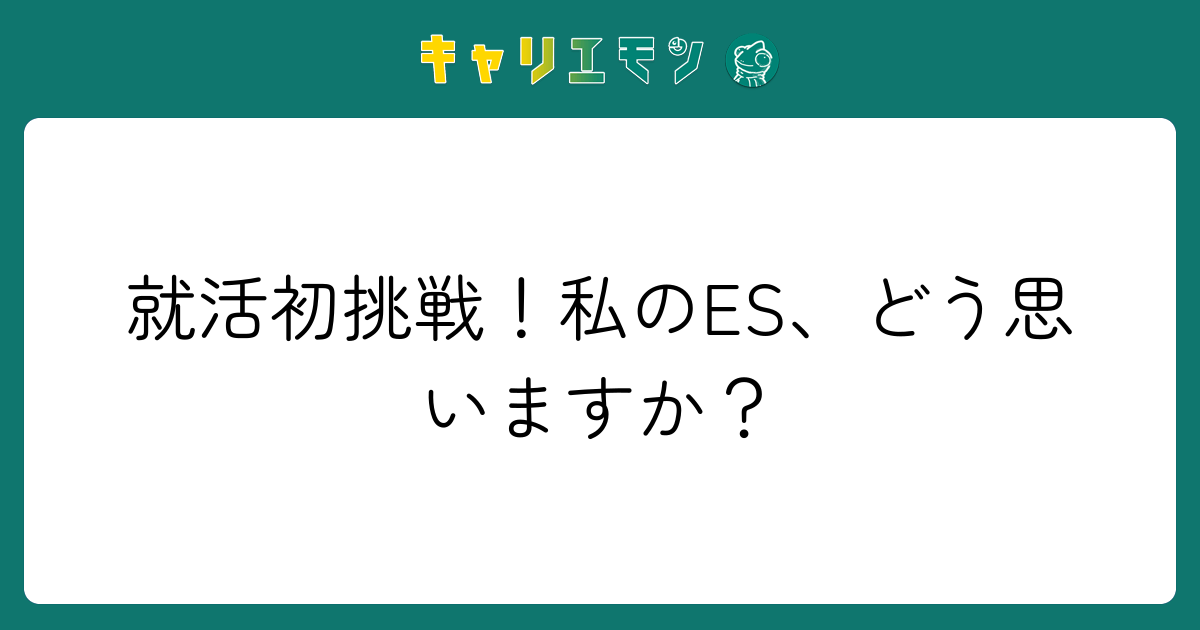
1
1人のサポーターが回答
相談・質問の内容|就活初挑戦!私のES、どう思いますか?
志望業界: 主にIT業界
志望職種: SEなど
どんな観点でどんなサポートをしてほしいか:
これから就活を始めていくので、某サービスの共通ESを作成しています。
とりあえず以下の内容で嘘や脚色なく作成しました。
長期間取り組んだことは研究しかありませんし、成果も現状ありません(一応、論文をジャーナルに投稿中ですが、通る保証はないです)。
どのような印象でしょうか、具体性に欠けますでしょうか。改善点等のコメントをいただけると幸いです。
またSE志望はチーム経験をアピールしたほうがいいと聞きます。そういった要素を含めるべきでしょうか。チーム経験については捻り出せますが、エピソードとしては弱く大した成果もありません。
詳しい相談内容:
自己PR 400字
私の強みは、探究心です。約4年間の研究室生活で、300本以上の論文を読みました。私の研究室では毎週、学生が持ち回りで論文の紹介と進捗報告を行うセミナーがありますが、聞き手は各発表について、必ず一度は質問しなければならないというルールが設けられています。配属当初は的外れな質問しかできず、研究分野に対する知識や理解の不足を痛感しました。それから、日々の実験の空き時間を利用して、少しずつ論文を読み、知見を蓄え続けました。その結果、徐々にセミナーでの質問の精度を上げていくことができ、最終的には本質的な質問を複数できるようになりました。論文の探し方や読み方が上達するにつれて、一層、研究分野が好きになり、常にアンテナを張って最新の情報をキャッチアップしていました。私はこのように自主的に専門性を高めていく姿勢で、仕事に取り組みたいです。
学生時代に最も打ち込んだこと 400字
私は研究に打ち込み、「守破離」の「守」を学びました。研究を始めたての頃、行き当たりばったりでなんとなく実験をしては、度々ミスやコンタミネーションを起こしていました。見かねた指導教官は私に「守破離」について説き、まずは基本に忠実であるように言いました。それからは、先輩や同期の実験を観察し、徹底的に真似をすることで、細かい所作一つ一つの意味を理解していきました。また、論文を読み、指導教官や他大学の研究者のアドバイスを積極的に自分の実験に取り込んでいくうちに、知識や技術は盗むものであるという感覚をつかむことができ、どのように実験を成立させるのかのプロセスを思考する癖がつきました。その結果、12時間以上かかる実験でもミスやコンタミネーションをしなくなり、私の研究の前任者3人ができなかった実験にも成功しました。この経験を通して、私は「守破離」の姿勢で物事に取り組むことの大切さを学びました。
キャリエモンを使ってみよう
プロのキャリアサポーターからガクチカや自己PR添削・志望動機添削・キャリア相談全般などを無料で受け放題!

回答タイムライン(1)
就活初挑戦!私のES、どう思いますか?
就活初挑戦!私のES、どう思いますか?
- Chinatsu Kato回答日: 2024年5月10日長期間取り組んだ内容として研究をエピソードにあげるのはとても良いと思います! 注目して頂きたいポイントは、企業がそのエピソードを読んだ際に「SEとしての活躍イメージができるか」という点です。 自己PRについてですが、自主的に知見を蓄え続けられること、最新の情報をキャッチアップする姿勢はSEにとってもとても重要な事だと思いますので、アピールの方向性としては良いと思います。 ただ、SEを目指されているという事であれば、研究と並行してプログラミングなどの勉強も行っていているなどの情報があったほうが、企業としても質問者様の「志望度の高さ」を伺うことができるため、今現在SEになるために行っていることがあれば、そちらに関しても記載することをおすすめします。 また、SEは基本的にチームで開発を行なう事になる為、チーム経験のアピールは確かに有効です。例えば研究について記載する中で、もし研究室のメンバーと連携をとって行う部分などがあれば、そういった様子についても記載するなどしてチーム内でのコミュニケーションを円滑に行えていた様子が分かるとより良いかと思います。 ガクチカにおいては、前任者3人ができなかった実験に成功したとのこと、素晴らしいですね! ただ、SEとしての開発でいくと 「守」はプログラム言語の仕様・アルゴリズムやロジックを覚えていく段階になるかと思います。 仕事で実際に活躍していく為には、その先の 「破」「離」の段階として、要求された仕様に対して最適なプログラミングを独自で行い、開発・実装していくということが必要になるのではないでしょうか。 その為、「守」で終わらせるのではなく、「守」を学んだうえで、その先にどうしていくかというところまで、 ご自身も企業もイメージができるようになると、より良いかと思いました。 少しでも参考になりましたら幸いです。