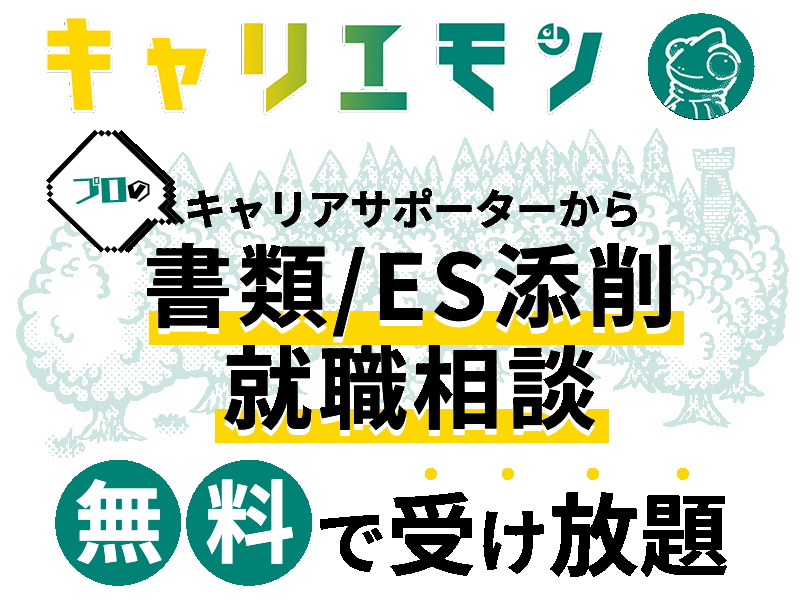ゼミ活動で学んだリーダーシップとは?|「ES全般」の相談
2025年3月に大学(学士)を卒業予定
21歳 男性
相談日: 2024年1月26日
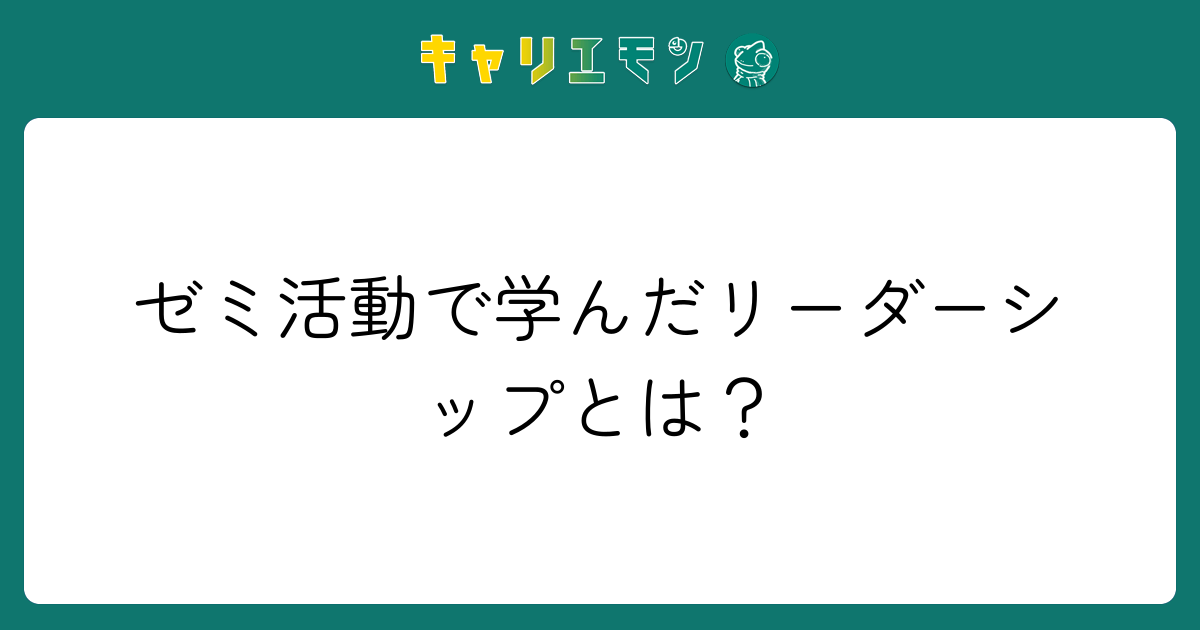
3
1人のサポーターが回答
相談・質問の内容|ゼミ活動で学んだリーダーシップとは?
ガクチカと自己PRを書いたのでフィードバックをいただきたいです。
ガクチカ
私は学生時代、ゼミ活動に力を注ぎました。ゼミでは、全国の大学から約120チームが参加するISFJ日本政策学生会議という大会での入賞を目指しておりました。全国の大学の看板ゼミが多く参加するため、どの視点でも矛盾のない研究にする必要がありましたが、当初は班員の対立もあり研究が進みませんでした。まず、徹底的な議論が必要と考えたため、ゼミ外の時間にも集まって意見をぶつけ合うことでそれぞれの考えをまとめ、全員が納得する方向性を考えました。これにより研究の方向性は固まりましたが、次は熱心に取り組まない班員が出てきて、研究を進めることに苦慮しました。そこで、班員全員と個々に連絡を取り、それぞれの得意なことをヒアリングして仕事を割り当てたり、時には誰も行わない業務を率先して行ったりして、リーダーとして班をまとめ続けました。結果、班がまとまり、大会では最高評価となる最優秀政策提言賞をいただくことができました。
自己PR
私の強みは粘り強く努力が出来ることです。大学2年生の時に統計学の授業を履修し、統計に興味を持ったことがきっかけで統計検定2級の取得を目指しましたが、当初は点数が取れず合格には程遠い状態でした。合格に向けて、学習時間が足りていないことが課題と考えたので、どれだけ忙しい日であっても毎日3時間以上の学習を自らに課し、勉強量を確保しました。また、基礎の不足も感じたため、問題集の基礎問題だけをピックアップしたオリジナル問題集を作成して解き続け、基礎が身に付いた後は、過去問15回分を試験前日まで覚えるくらいに解き続け知識の定着を図りました。それに加えて、同じ資格を目指すゼミの仲間を誘って、統計の勉強会を開催し、苦手分野を教え合ったり、採点しあったりすることで、互いの成長に繋げました。このような取り組みを継続した結果、徐々に成績も安定し、試験では一発合格することが出来ました。この強みを貴社でも活かします。
キャリエモンを使ってみよう
プロのキャリアサポーターからガクチカや自己PR添削・志望動機添削・キャリア相談全般などを無料で受け放題!

回答タイムライン(3)
ゼミ活動で学んだリーダーシップとは?
ゼミ活動で学んだリーダーシップとは?
- (株)UZUZ代表取締役 岡本啓毅回答日: 2024年1月27日エピソードを伝える際には、そのエピソードを伝えた結果「そんなに素晴らしい取り組み方をして、素晴らしい結果を出しているのであればうちの会社でも活躍してくれそうだな!」と思ってもらえるように伝えることが大切になります。 ガクチカの取り組み内容としては >班員全員と個々に連絡を取り、それぞれの得意なことをヒアリングして仕事を割り当てたり、時には誰も行わない業務を率先して行ったりして、リーダーとして班をまとめ続けました。 という内容ですが、より成果につながるイメージを持ってもらえるような具体性を持たせられると良いと思います。 現在の内容は抽象度が高く「確かに、それをやれば120チーム中1番の評価をもらえるだろうな!」と感じてもらうのは少し難しいように感じます。取り組んだ量、質、メンバーへの働きかけなどの側面から、120チームの中で1番になることにつながった要因をわかりやすく伝えられるとグッとパワーアップできると思います。 自己PRの取り組みは目指されているデーターサイエンティストでの活躍イメージに直結する取り組みになっていてとても良いと思います。ここからさらにパワーアップできるポイントとしては、「資格取得」のその先の成果まで範囲を拡張できると良いのではないかと思います。 ゼミでも統計学について学ばれていたとのことなので、資格取得で伸ばした統計学のスキルを活かして研究で上げた成果などについても伝えられると「しっかりと継続的な努力をして、実務にも活かしてくれそうだな!」とより感じてもらいやすくなるのではないかと思いました!
- 相談したユーザー返信日: 2024年2月3日ガクチカ書き直してみたのでフィードバックいただきたいです。 私は学生時代、ゼミ活動に力を注ぎました。ゼミでは、全国の大学から124チームが参加するISFJ日本政策学生会議という大会での入賞を目指しておりました。全国の大学の看板ゼミが多く参加するため、どの視点でも矛盾のない研究にする必要がありましたが、当初は班員の対立もあり研究が進みませんでした。まず、徹底的な議論が必要と考えたため、ゼミ外の時間にも集まって意見をぶつけ合うことでそれぞれの考えをまとめ、全員が納得する方向性を考えました。これにより研究の方向性は固まりましたが、次は熱心に取り組まない班員が出てきて、研究を進めることに苦慮しました。そこで、班員全員と個々に連絡を取り、それぞれの得意なことをヒアリングして仕事を割り当てたり、毎日10時間以上研究に取り組んだりしてリーダーとして班をまとめ続けました。結果、班がまとまり、大会では最高評価となる最優秀政策提言賞をいただくことができました。(396)
- (株)UZUZ代表取締役 岡本啓毅回答日: 2024年2月3日>どの視点でも矛盾のない研究にする必要がありました とのことなので、取り組み内容として伝える際には「確かにそのような取り組み方をするとどの視点でも矛盾は無くなるだろな!」と感じてもらえるような伝え方をすることが大切になると思います。 現在の内容は、一般的なリーダーの進め方の話になっていて「どの視点でも矛盾がなくなって124チーム中最優秀賞を取れるだろうな!」とまでは感じてもらいづらいように感じます。 例えば、「それぞれの担当が作った部分に対して、そのほかのメンバー全員が最低10個は論理矛盾がないかを指摘するといったルールを作り、小さな矛盾も残さないようにしました」などの、「そこまでやりきれば、論理矛盾は無くなるだろうな!」と感じさせるような具体性を持たせると、グッと解像度があって説得力が増すのではないかと感じました!